

緑ゆたか 落ち着いた山里
春は山桜 初夏にはホタル
山田方谷ゆかりの史跡が残る里
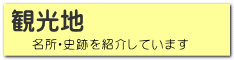
| 見 返 り の 榎 |
|
  |
1859年7月越後長岡藩の藩士 河井継之助が方谷先生に弟子入りするためにこの長瀬を訪れました。先生に気に入られ、翌年3月までの期間松山に滞在、花屋とか水車、ときには長瀬に寝泊まりして先生の改革手法を目の当たりするとともに、弟子たちとも親交を深め大きな収穫を得、自身も成長し、心から先生に心酔するようになりました。 そして、別れの際、門外まで見送りに出た山田家の人々と別れを惜しんだ後、先生から譲り受けた「王陽明全集」と、お酒を入れた瓢箪を振り分け荷物にし、先生からいただいた「長命丸」をふところにした継之助は、従僕柴倉浅太郞のあやつる船に乗り対岸に渡ると、河原に手をついて何度も何度も土下座し、川下に向かって歩を進め遠ざかっていきました。 一方、先生は一同声も無く感激に包まれ、凝然として姿が見えなくなるまで門の外で手を振っていました。この様子を見ていたのが、 この「榎」なのです。 余談ながら継之助は帰国後、家老になり藩政改革にも成功しました。しかし、心ならずも奥羽列藩同盟に参加することとなり、北越戦争で受けた傷がもとで42才の若さで帰らぬ人となりました。その間際、出入りの人夫請負人 松屋吉兵衛に「もし先生に会えることがあったら河井はこの場にいたるまで方谷先生の教訓を守ってきたことを伝えてほしい」と語ったそうで、妻「すが」さんも「河井は山田先生を神のごとく尊敬し信じておりました。床の間に先生の書幅を掲げ毎朝礼拝を欠かしたことなど一度もありませんでした」と述べておられます。後年、河井家の家族が長岡の住人に厳しい仕打ちを受けていると伝え聞いた先生は、「当方へお移りなされてはいかがですか」とお誘いしましたが、親戚をたよって北海道へと移られました。また、河井継之助の遺族より碑文を依頼されたとき、先生は断っています。そして、「河井家より蒼竜洞の碑文を頼まれし時」と前置きして、「碑を書くもはずかし死に遅れ」の俳句を残しています。そのため碑文は三島中洲が撰文「故 長岡藩総督 河井君碑」として新潟県長岡市の悠久山に建っています。 |
   |
|