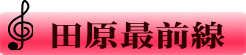
虎は、古来から日本には生息していません。虎はいつ日本に来たのでしょうか。
虎という文字が見られる文献を調べてみると、日本書紀に、欽明天皇6年(545)11月のこと、膳臣巴堤使(かしわあでのおみはてし)が、百済に使いして虎を退治し、その皮をはぎとって持ち帰ったと記しているくだりがみられます。
その後のことはよくわかりませんが、後陽成天皇文禄3年(1594)12月、朝鮮の役に従事した吉川広家が豊臣秀吉に虎を送り、秀吉はこれを宮中に運んで天覧に供したと伝えられ、慶長7年(1602)には、校祉から生きた虎を1頭、象1頭、孔雀2羽を徳川家康に送っています。
また、慶長18年(1613)8月には蘭人が駿府(静岡)の徳川家康に虎の子を2頭送っています。
こうしてみてみますと、政治的な含みで当時の偉い人のみが生きた虎をみることができたわけですが、庶民はほとんど虎などを知る由もなかったと考えられます。
では、庶民はいつ頃から生きた虎を知るようになったのでしょう。
生きた虎が見世物として登場するのは延宝3年(1657)の版本『芦分船』の大阪・道頓堀見世物の条に「虎のいけどり」があり、さらに『摂陽年鑑』にも「延宝年中虎の生捕りとて、大坂に於いて諸人に見せしむ」とありどうやらこれが最古のようですが、どうでしょうか、当時のこと、虎が真実の虎かどうかははっきりしなかったのではないでしょうか。
明治15年(1882)、東京上野動物園が開園し、明治19年にイタリアの曲馬団チャーネリーの一座が、秋葉原で興行中、連れていた虎が子供を生み、この虎が上野動物園で飼育されました。
この頃からは、虎は珍しくなくなってきたのだと思います。
毎年新しい年への期待と願望を込めて干支の玩具が製作されます。
『和漢三才絵図』には「十二支所属之獣尚未解、其字義尽解、多此仮借」とあるとおり、なぜ十二支がねずみに始まり12の動物をあてはめたかはよくわかっていません。
しかし、自分の生まれ年に因んだ干支の動物を縁起のお守りとして身につける習慣があり、干支の玩具はこうした民間信仰に支えられて、郷土玩具の中に大きな分野として育ってきたといえます。
中でも、ねずみ、牛、馬、にわとり、犬などは、人間生活に関係が深いところから縁起ものとして数多くの玩具が作られてきました。
これとは対照的に元来日本に生息していなかった動物で、しかも猛獣で、実物にも触ったことがなく、余り親しんだこともなかったはずの虎であるにもかかわらず、虎を扱った玩具は不思議なほど多く、ゆったりと首を振る張り子の虎は各地で高い人気を得て受け継がれています。
神社や寺院では、その年の干支を表現した絵馬、土鈴など、さらに年賀はがきや年賀切手などに干支が用いられ、干支に対する伝統は根強く続いています。
僅かの文献をみただけではありますが、考えてみるに、江戸時代以前に張り子が登場していたとするならば、園時代はすでに社会全体が現在のようでなくても在る程度成熟していなければならなかったのでないでしょうか。
古来から虎が魔を除くという由来がありますが、虎骨が薬用となり、その虎骨は頭風を治すという俗説に基づき、中国では皇子降誕の時に虎頭をまつり邪気を退ける慣例がありました。
日本でも、『御産所日記』に「永享6年2月11日午後 御湯治 虎8入杓御湯具」と記載されています。
このことから、魔除けとして姿をみせた張り子が、やがて節供など暮らしの中で位置付けられ、神社やお寺の参拝客の土産、子供相手のおもちゃなどとして普及したと考えられます。
したがって、玩具の製作者、販売者、購買者の存在といった形があったのではないだろうかと考えられます。 しかし、大衆のものが張り子を発見するのは江戸時代、つまりは商業が活発になりだしたこの時代に入ってからだという推測は無理がないはずだと思います。
元来日本には生息しない虎が玩具として現れた文献は、貞享4年(1687)版行の井原西鶴の『男色大鑑』(本朝若風俗)の第7巻の中に「道頓堀の真斉橋に人形屋新六と言へる人、手細工に獅子笛あるいは張貫の虎、またはふんどしなしの赤鬼、太鼓もたぬ安神鳴これみな童子たらしの様に・・・」の一節があります。
貞享4年といえば、今から300年ほど前でありますから、その当時すでに虎玩が製作されていたことになります。
その後、安永2年(1773)版行の江戸時代唯一ともいえる玩具絵本である『江都二色』の中に約80種の玩具図が描かれていますが、このうち第20図に犬張子と張り子の虎が描かれています。
ちなみに虎玩といえば張り子の虎のことです。
張り子は中国から伝来した新しい人形づくり文化だと言われています。
前述したとおりの文献では、中国から伝来したということは記載されていませんが、江戸時代以前ということは間違いないと思われます。
山城国の地誌『』には江戸時代初期の張り子づくりの詳細が報告されています。
その内容は、「凡ソ木ヲ以テ人形及ビ鳥獣ノ形状 ニ緒ノ模範ヲ造リ、然テシテ後ニ稀糊ヲ白紙ニ貼シテ、其外面ヲ張ルコト数編、日ニ乾シテ後、縦或イハ横ニ之ヲ中分シ、小刀ヲ以テ張ル所ノ中間ヲ リ二ツニ之ヲ別ケ、爾ル後再ビ之ヲ合セ函蓋ト為ス。是ヲ張子ト謂フ。 (途中略) 内ニ在ル所ノ模範ヲ出シ、別ニ紙ヲ以テ合縫ノ間ヲ補 シテ全形ト為シ、彩色ヲ其ノニ施シ、面顔衣服ノ彩ヲ分ツ。是ヲ張脱細工ト称ス。」 と書かれ、現在の張り子と殆ど変化はしていないようです。
虎の張り子は北は青森県から南は沖縄県まで全国津々浦々にわたっています。生産地も以前は80にも及んでいたといわれます。
江戸、京都、大阪周辺などに生産地が多く、張り子が消費地をにらんで生産されていたことが推測されます。
爆発的な人気を保持した張り子は度後で最初に生産されたのでしょう。
張り子製作には先ずその材料となる紙が必要となります。昔の紙は反古紙といえども大変貴重品であったと思います。
張り子の本格的な普及は江戸時代ですが、それより以前に生産されたとするならば、材料となる反古紙、この反古紙が大量にでるところではなかったかとおもいます。すると政治・経済の中心であった京都、そして商業の中心であった大阪であったはずです。この両地では繁栄と共にたいりょうの紙が使用され、比例して大量の反古紙がでたと考えられます。
商売熱心な大阪人がこれを利用しないはずがなく、後述しますが、政治の中心であった京都でなく大阪であったと推測するのであります。
大阪で作られ大阪の問屋を通じて全国に流れたものであろう。
その後、各地の城下町や商業地などで反古紙の入手の容易な所から生産地が生まれそれは幕末から明治に入ってからだと考えます。
この一考察についてのお問い合わせは本紙までどうぞ
縁起物についての一考察
全国の郷土玩具を集め初めて20年。特に虎の玩具に集中しているつもりではいますが、縁起物も数多くになり、機会を見て町内のイベントなどでも展示、公開しています。七転び八起きの福だるまや、酉の市の熊手、客寄せの猫と言えば、商売繁盛、開運招福を約束する縁起物のベスト3でしょう。
商売あるところに必ず縁起物があり、利の追求の為には合理化、効率主義の精神のみならず、それらと相反して非合理主義的な縁起担ぎもまた求められているのだろうか。合理主義をもってしても完全に予測することができず、人の運命にしてもまたそうであろう。それは神のみぞ知ることであるう。
よりよい将来の切り開かれんことを祈って願いを込め、ある信仰物にその思いを託すことを単なる迷信だと言ってしまえばそれまでですが、人の心は簡単に割り切れませんよネ。
商売や経済の世界のみならず、私たちがこの世に生まれ、幸せな人生を送りたいと望みつづける限り、さまざまな欲望や、願望はいくらでも生み出されます。病気が癒されること、健康で長寿であること、縁が結ばれ夫婦円満であること、子宝に恵まれ、安産で子育ても順調なこと、受験戦争にも交通戦争にも勝ち残ること、なかには立身出世で富を築くことなど。
これらの数限りない人々の願いを叶えるために生み出されたものが、仏教でもない、神道でもない日本独特の民間信仰、縁起物そのものであると思います。私たちは縁起担ぎであります。些細なことにも縁起の善し悪しを気にし、安心を得るために大金もはたきます。不景気な世の中だからこそ、一丁奮起して大きな熊手を買ったりします。古来から様様な縁起物が生み出されています。今年も縁起物収集の旅を続けます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日本中に郷土玩具館、美術館、陶器などを集めた博物館がたくさんありますよね。これらの多くは私的に集めたコレクションが大掛りになったもの。
皆さんは、どんなものを集めていますか。旅先のこけしや絵葉書、喫茶店のマッチ、箸袋、数さえ集めれば立派になコレクション。
継続していくと夢が実現します。骨董品の中には昔はまったく価値の無かったものでも、現代では希少価値が出ているものもあります。自分にはまったく儲けにならなくても、子孫がもうかるといったことになるかもしれませんよ。
年賀切手になった郷土玩具展 作品一覧(2007/12月高梁市本町のいきいきプラザで開催した)
年賀切手になった郷土玩具展 作品一覧(2008/1月成羽町吹屋公民館で開催した)
年賀郵便切手
新年を寿(ことほ)ぐ習慣は古くからありますが、郵便による年賀状の交換は、今日では欠かすことのできない迎春の恒例風習となっています。年賀郵便切手は、昭和11年(1936年)の年賀用として昭和10年(1935年)に初めて発行しました。その後、一時の中断がありましたが、昭和23年(昭和24年用)以降、毎年発行されています。
|
作 品 名 |
県 名 |
年 |
干 支 |
| 1 |
米食いねずみ |
石川県 |
昭和35年 |
子(ね) |
| 2 |
小槌乗りねずみ(小幡人形) |
滋賀県 |
昭和59年 |
子(ね) |
| 3 |
唐辛子乗りねずみ(堤人形) |
宮城県 |
平成8年 |
子(ね) |
| 4 |
米倉ねずみ(薩摩首人形) |
鹿児島県 |
平成8年 |
子(ね) |
| 5 |
赤べこ |
福島県 |
昭和36年 |
丑(うし) |
| 6 |
金のべこっこ |
岩手県 |
昭和36年 |
丑(うし) |
| 7 |
作州(吉備)牛 |
岡山県 |
昭和60年 |
丑(うし) |
| 8 |
闘牛(沖縄張り子) |
沖縄県 |
平成9年 |
丑(うし) |
| 9 |
牛乗り子供(高松嫁入り人形) |
香川県 |
平成9年 |
丑(うし) |
| 10 |
張り子虎 |
島根県 |
昭和37年 |
寅(とら) |
| 11 |
神農の虎 |
大阪府 |
昭和61年 |
寅(とら) |
| 12 |
三春張り子虎 |
福島県 |
平成10年 |
寅(とら) |
| 13 |
博多張り子虎 |
福岡県 |
平成10年 |
寅(とら) |
| 14 |
ウサギ(のごみ人形) |
佐賀県 |
昭和38年 |
卯(う) |
| 15 |
餅つきうさぎ(佐原張り子) |
千葉県 |
平成11年 |
卯(う) |
| 16 |
辰(岩井挽物人形) |
鳥取県 |
昭和39年 |
辰(たつ) |
| 17 |
たつぐるま |
福島県 |
昭和51年 |
辰(たつ) |
| 18 |
辰(倉敷張り子) |
岡山県 |
昭和63年 |
辰(たつ) |
| 19 |
飛龍(からつ曳山人形) |
佐賀県 |
平成12年 |
辰(たつ) |
| 20 |
辰(常石張り子) |
広島県 |
平成12年 |
辰(たつ) |
| 21 |
土鈴の蛇(下野土鈴) |
栃木県 |
昭和64年 |
巳(み) |
| 22 |
うずまき巳(深大寺土鈴) |
東京都 |
平成13年 |
巳(み) |
| 23 |
三春駒 |
福島県 |
昭和29年 |
午(うま) |
| 24 |
忍びの駒 |
岩手県 |
昭和41年 |
午(うま) |
| 25 |
飾り馬(浜松張り子) |
静岡県 |
平成2年 |
午(うま) |
| 26 |
八幡馬(駒) |
青森県 |
平成2年 |
午(うま) |
| 27 |
吉良の赤馬 |
愛知県 |
平成14年 |
午(うま) |
| 28 |
すげの稲馬 |
新潟県 |
平成14年 |
午(うま) |
| 29 |
八幡起き上がり |
石川県 |
昭和30年 |
未(ひつじ) |
| 30 |
ひつじ鈴(中山人形) |
秋田県 |
昭和54年 |
未(ひつじ) |
| 31 |
羊鈴(のごみ人形) |
佐賀県 |
平成3年 |
未(ひつじ) |
| 32 |
羊(常石張り子) |
広島県 |
平成3年 |
未(ひつじ) |
| 33 |
扇持ち未(会津中湯川人形) |
福島県 |
平成15年 |
未(ひつじ) |
| 34 |
干支 未(邑久張り子) |
岡山県 |
平成15年 |
未(ひつじ) |
| 35 |
未(江戸趣味小玩具) |
東京都 |
平成15年 |
未(ひつじ) |
| 36 |
延岡の昇り猿 |
宮崎県 |
昭和43年 |
申(さる) |
| 37 |
猿の三番叟 |
石川県 |
平成4年 |
申(さる) |
| 38 |
桃持ち猿(小幡人形) |
滋賀県 |
平成4年 |
申(さる) |
| 39 |
三番叟(伊予一刀彫) |
愛媛県 |
平成16年 |
申(さる) |
| 40 |
出世猿(姫路張り子) |
兵庫県 |
昭和44年 |
申(さる) |
| 41 |
トリ(笹野一刀彫) |
山形県 |
昭和44年 |
酉(とり) |
| 42 |
にわとり(中野人形) |
長野県 |
昭和56年 |
酉(とり) |
| 43 |
にわとり(紙塑民芸品) |
富山県 |
平成5年 |
酉(とり) |
| 44 |
太鼓乗りにわとり(津屋崎人形) |
福岡県 |
平成5年 |
酉(とり) |
| 45 |
十二支酉(日田土鈴) |
栃木県 |
平成17年 |
酉(とり) |
| 46 |
十二支とり(下野土鈴) |
栃木県 |
平成17年 |
酉(とり) |
| 47 |
犬張り子 |
東京都 |
昭和33年 |
戌(いぬ) |
| 48 |
守り犬 |
奈良県 |
昭和45年 |
戌(いぬ) |
| 49 |
犬(相良人形) |
山形県 |
昭和57年 |
戌(いぬ) |
| 50 |
犬(芝原人形) |
千葉県 |
平成6年 |
戌(いぬ) |
| 51 |
土佐犬(香泉人形) |
高知県 |
平成6年 |
戌(いぬ) |
| 52 |
イノシシ(すげ細工) |
新潟県 |
昭和46年 |
亥(い) |
| 53 |
ししのり金太郎(堤人形) |
宮城県 |
昭和58年 |
亥(い) |
| 54 |
亥(出雲張り子) |
島根県 |
平成7年 |
亥(い) |
| 55 |
宝珠の亥(江戸趣味小玩具) |
東京都 |
平成19年 |
亥(い) |
| 56 |
福徳ねずみ(奈良井土鈴) |
長野県 |
平成20年 |
子(ね) |
| 57 |
,ねずみ土鈴 |
山梨県 |
平成20年 |
子(ね) |

|