| その発見は1冊の論文から始まった。「毎日グラス1杯半の赤ワインを飲み続けると 脳の機能を改善する可能性がある」と、イタリアで発表された。 それを知った佐藤博士はある疑問を抱いた。 |
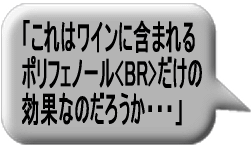  NEDOアルコール事業本部開発企画課課長医学博士 佐藤充克 |
葡萄の豆知識(その1)〜果肉の話〜
「ペンタ・ペプチド」
〜フジテレビ『発掘!あるある大辞典』より引用〜
| その発見は1冊の論文から始まった。「毎日グラス1杯半の赤ワインを飲み続けると 脳の機能を改善する可能性がある」と、イタリアで発表された。 それを知った佐藤博士はある疑問を抱いた。 |
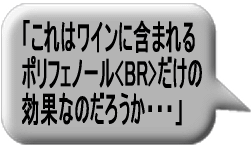  NEDOアルコール事業本部開発企画課課長医学博士 佐藤充克 |
| 仮説 |
発見 |
| 『葡萄にはポリフェノールだけではなく色々な物が入っている。もっと他に脳機能を改善する物質があるのではないか。』 | ポリフェノール以外に、「何か他の脳機能を改善する物質が含まれているのでは」と研究を続けた佐藤博士は、ついに果肉の中から、今まで知られていたものとは全く違った物質を見つけだしたのである。→ペンタ・ペプチド |
| 構造 |
ペンタペプチドとはアミノ酸が5つ繋がった物質。消化吸収が早く、神経伝達物質と似た構造を持っています。そしてその構造により現代人の多くが抱える脳機能低下を防いでいたのです。 | ▼PEP ●作用● 本来、PEPとは外から入ってくる膨大な情報で脳がパンクしないように作用する重要な物質。 ●脳疲労● しかし、情報過多の時代、我々の脳は疲れ気味。脳疲労が慢性化している人たちも増加傾向にあると言われ、その上睡眠不足などによるストレスも相乗的に働く事でPEPが必要以上に増えてしまいます。 すると本来必要だったPEPは一転、脳内で現代の悪役的な存在になってしまうと考えられているのです。 暴走したPEPは、神経細胞から出された神経伝達物質を必要以上に分解して、情報の伝達を阻害し記憶力を低下させてしまいます。 |
役割
|
では、一体ペンタペプチドはどのような作用をするのか? 例えばこんなことはありませんか? ・頭がボーっとする ・物忘れが多くなったなど 実はこれは脳内でPEPという物質が大量発生するためだと考えられている。 そこで活躍するのがペンタペプチド。摂取されたペンタペプチドは神経伝達物質と似ている特徴から、身代わりとなって神経伝達物質が分解されてしまう前にPEPと結合。 すると、伝達の発信基地であるシナプスはPEPに邪魔されずに神経伝達物質を活発にやりとりすることが可能となり、脳の機能をアップすることが出来るのです。 |
■ ■ ■ ペンタペプチド効果的摂取法 ■ ■ ■
葡萄の果肉に含まれる脳機能を改善させるというペンタペプチド。
一体どの葡萄に多く含まれているのでしょうか?
| 『ペンタペプチドを発見したのはつい最近。どの葡萄にどれだけ入っているのかはまだ全く分かっていない。』 <NEDOアルコール事業本部開発企画課課長医学博士 佐藤充克> そこで、『発掘!あるある大辞典』では、番組独自にペンタペプチドの含有量を以下の5種類の葡萄について検査。 結果、今回分析した5品種(巨峰・デラウェア・ピオーネ・マスカット・ルビーオクヤマ)の中では特にピオーネに多く含まれていることが判明! |
||||
| ピオーネ | 巨峰 | デラウェア | ルビーオクヤマ | マスカット |
| 約1/7房 (約4粒) |
約1/3房 (約12粒) |
約3房 | 約3房 | ― |
| 現段階では、1日に0.2mg摂取すれば脳機能に効果的といわれるペンタペプチド。 ワインの場合ボトルをおよそ1本飲む必要がありますが、ピオーネであればおよそ4粒、巨峰であれば12粒でOK! |
||||
葡萄の豆知識(その2)へ 葡萄の豆知識(その3)へ ホームへ
All pages produced by ATSushi & TELko Morita