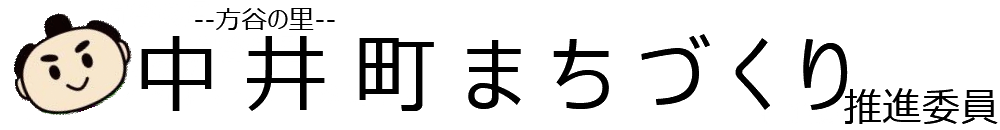方谷先生とは?

山田方谷
文化二年(1805)高梁市中井町西方に生まれる。名は球、通称安五郎。 父は五郎吉、母は梶。 五歳の時、親元を離れ新見の丸川松隠の元で学ぶ。 九歳の時、松隠を尋ねた客が方谷に「学問をして何をするのか」と聞かれ「治国平天下」と答え驚かす。 方谷十四歳で母が、翌年父が亡くなり家業を継ぐ。貧しい生活であったが学問への情熱を失わず、この噂が藩主の耳に入り二十一歳の時、二人扶持(一日玄米一升)を与えられ、藩校有終館で学ぶことを許される。 二十三歳から三十歳までの間、四回に亘り京都、江戸へ遊学する。江戸遊学では佐藤一斎の門に入り塾頭を務めた。同門に佐久間象山がいたが、方谷が常に論戦を打ち負かした。また、有終館では苗字帯刀を許され、会頭を命ぜられる。 三十二歳には有終館学頭となった。 四十五歳の時、藩主 勝静から「元締役、および吟味役」を命ぜられる。ここから方谷の財政改革が始まる。 松山藩は五万石とはいうものの、実際は一万九千石余り(藩士領民への渡し米を除くと年間収入は一万九千両)に過ぎず、この時既に借入金は十万両となり、利息だけでも年間九千両必要であった。そこで方谷は、次の六項目を掲げ、わずか八年で十万両の借金を払うどころか、十万両の余財を残すまでになった。

安政六年(1859)、この頃方谷は長瀬(現方谷駅)に私塾を開いていたが、長岡藩士 河合継之助が来訪し方谷に学ぶ。以後継之助は方谷を一生の師と仰いだ。 文久元年(1861)、藩主 勝静は奏者番兼寺社奉行、翌年には老中となり、その間方谷は顧問となる。 慶応三年(1867)大政奉還が行われたが、その原文を方谷が作成する。 明治以降、たびたび政府から出仕の要請があったが、晩年の方谷は、閑谷学校の再建や、各地に塾を作り教育へ情熱を注いだ。 母の出身地の小坂部で塾を開いていたが、明治十年(1877)多くの塾生に見守られて永眠する。亡骸は西方村に移され埋葬された 明治四十二年に方谷の偉業を後世に伝えようと墓地の前に庭園を造成した。これを「方谷園」と命名した。入り口にある「方谷園」の文字はこの日来園し後に首相となった犬養毅の揮毫したものである。
ほうこくん

山田方谷先生をモデルに作られた中井町のご当地ゆるキャラ
右手に「備中鍬」、左手に財政改革について書いた「理財論」を持っている。服は自然の豊かさをイメージした緑、特産ピオーネの紫に山田家の家紋があしらわれている。
着ぐるみになったり、シールになったり、神社になったりと大忙し。